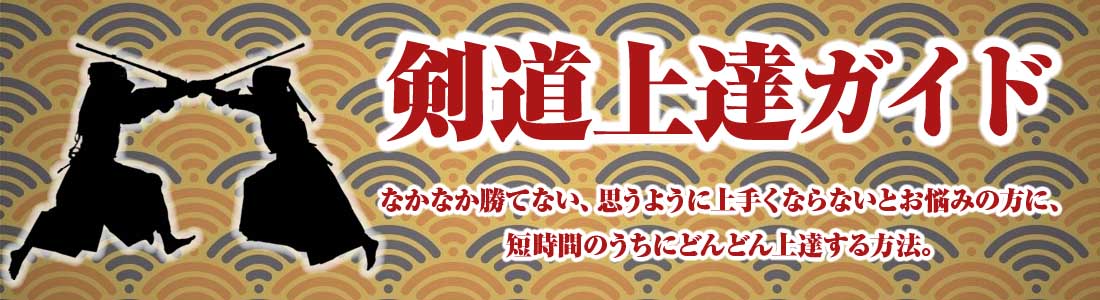剣道基本技稽古法
構え
目付け
間合い
打突
足さばき
掛け声
残心
一本打ちの技
「正面」「小手」「胴(右胴)」「突き」
連続技
「小手」⇒「面」
払い技
「払い面(表)」
引き技
「引き胴(右胴)」
引き技
「面抜き胴(右胴)」
すり上げ技
「小手すり上げ面(裏)」
出ばな技
「出ばな小手」
返し技
「面返し胴(右胴)」
打ち落とし技
「胴(右胴)打ち落とし面」
剣道目からうろこの上達法
「正面」「小手」「胴(右胴)」「突き」
「小手」⇒「面」
「払い面(表)」
「引き胴(右胴)」
「面抜き胴(右胴)」
「小手すり上げ面(裏)」
「出ばな小手」
「面返し胴(右胴)」
「胴(右胴)打ち落とし面」
昭和50年3月20日制定 全日本剣道連盟
股割り素振り
踏み込み素振り
切り返しは面打ち、体当たり、左右面などの基本を組み合わせた総合稽古です。
まず、一足一刀の間合いから、
これを二度繰り返し、最後にもう一度面を打って終わります。
相手に面を打つと思わせ、手首を返して胴を打つ。

素振りは剣道において最も基本で重要となる練習です。
毎日欠かさず続けましょう。
 基本の足の構え方
基本の足の構え方
・両足に等しく体重をかけ重心は身体の中心に置く
・両足の間隔はこぶし1つ分
・右足のかかとと左足のつま先が同じラインにくるように
・右足をやや前に出しかかとを薄紙一枚分上げる
・左足かかとは軽く上げておく
・この時左足が外を向かないように
足さばきは基本全てすり足で行います。
 竹刀の握り方
竹刀の握り方
・左手は柄頭いっぱいを小指と薬指でしっかり握る
・右手は人差し指が鍔に触れる程度のところで柔らかく握る
・両手とも薬指と小指でしっかり握り、他の指は軽く添えます。
・力の入れ加減は、左手7割、右手3割を意識。
・柄皮の縫い目に両手の親指と人差し指の根元を合わせます。
・親指と人差し指の付け根の股部分が真上に来るように持つ
・右手の人差し指が鍔に少し触れるくらい
・左手の小指が柄頭に半分くらい掛かる位置
・小指・薬指・中指の順に力を入れる
・ 親指・人差し指は軽く添えるくらい
 構えは基本中の基本、正しく構える事が大事です。
構えは基本中の基本、正しく構える事が大事です。
・肩の力を抜き、下腹部(丹田)を意識しながら腹式呼吸をする。
・背筋をぴんと伸ばし前かがみにならないように。
・無理なくゆったりと自然体で構えることが重要です。
・目線は相手全体を見るようにする。
・両足に等しく体重をかけ、重心は身体の中心に置く。
・左こぶしはへその高さに置き、中心から外さない。
・脇は胴から離す。
・半身にならないよう左腰を入れる。
・つま先を相手に向ける。
・剣先は延長線上が相手の目線の高さになるように構えます。
 ●礼儀作法がしっかりする。
●礼儀作法がしっかりする。
剣道において何より大切なのは「礼儀」です。
ちゃんとした指導を受けた方は、
人に接する時に挨拶や会釈が自然に行えるようになります。
 ●大きな声で、はっきりしゃべれるようになる。
●大きな声で、はっきりしゃべれるようになる。
また、「最近の子どもは大きな声を出すことがないから声が小さい」
といわれますが、剣道では腹から声を出す訓練をします。
腹から声をはっきりと出して話をすると、
自信があるように見え、面接などでも印象が良いようです。
特に、警察官や自衛官になられる方には絶対有利です。
 ●忍耐力がつく。
●忍耐力がつく。
重い防具を身に付け、声を出しながら動くのは、
想像以上につらくて、厳しいものがあります。
でもそんなつらい練習をくぐりぬければ、
多少のことでは揺るがない忍耐力が身に付きます。
●他にも剣道ならではの魅力があります。
現在生涯スポーツが注目されていますが、剣道ではは70歳のおばあちゃんが、
小学生の男の子と一緒に剣道をやっている姿を目にしたりします。
剣道教室では老若男女問わず、全員一緒に剣道をやっているところが多くあります。
対人競技でこの状況は、剣道以外にあまり無いでしょう。
柔道などは男女別で練習していますし、体重などによっても分けられている場合があります。
男女関係なく年をとっても続けられる
そういったところも剣道の良いところないのではないでしょうか。

毎日一生懸命稽古しているのになかなか勝てない、思うように上達しない。そうお悩みではありませんか?それはもしかすると練習法が良くないのかも知れません。間違った稽古を続けていると、上達しないばかりか悪い癖がついてしまう恐れすらあります。思い切って稽古を見直して見ることで道が開けることもあります。ここにご紹介する教材は、剣士としても師範としても、日本を代表する先生による正しい練習法、上達法のDVDです。普段指導を受けることの叶わない遠い存在である先生の教えを受ける事が出来ます。